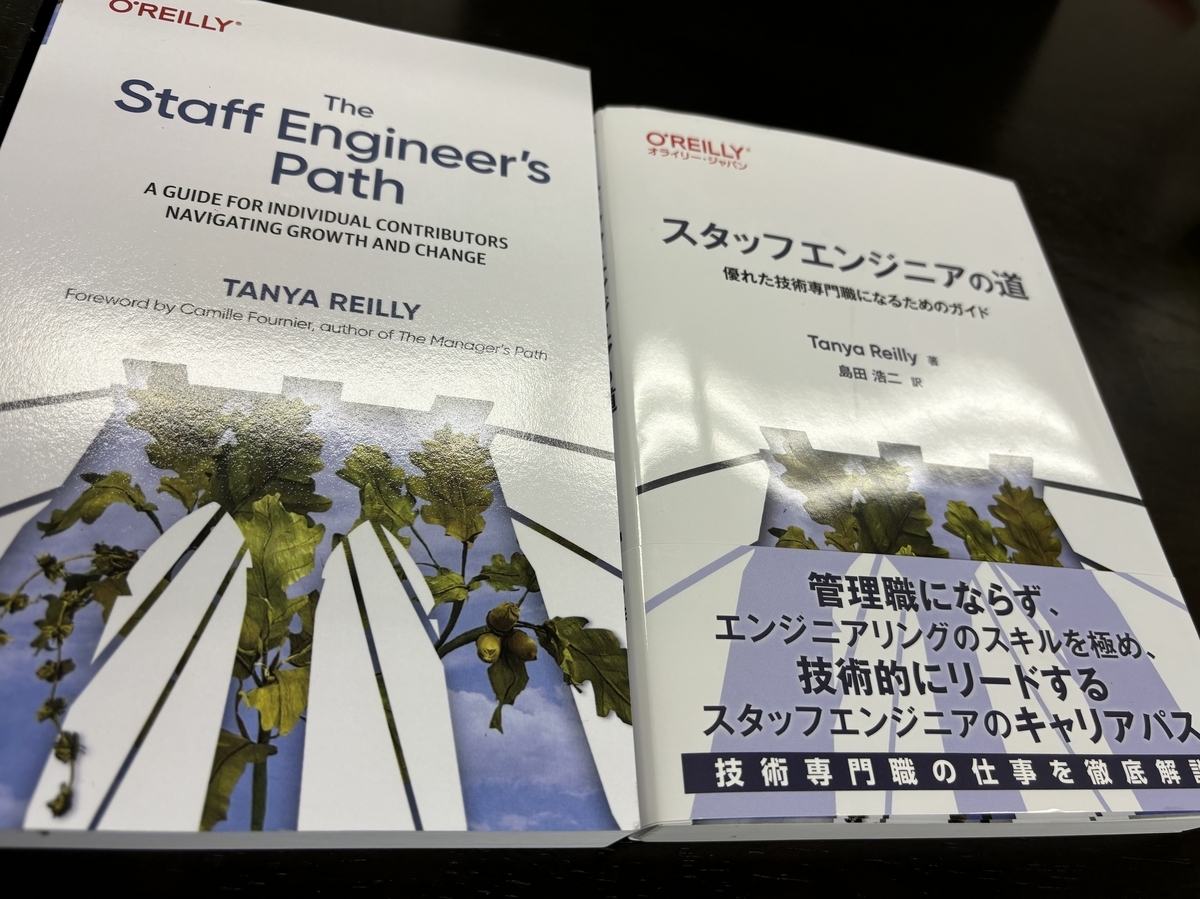↓↓詳細
雑な文。
CfP期間が始まったよ〜ということで、今回もワイワイとプロポーザルを書いたり出したり考えたりしているのだけど、その時に何となく思ったことを書き残しメモ。
昨年までは、「マネージャーになって仕事でコード書かなくなったので、話せるネタが無くなっちゃったんです〜」というのは自分にとってはダサい!!という気持ちがあり*1、ちゃんと出し続ける事を大事にしたいなぁって思っていたり。
社内で他人に「出してみようよ〜楽しいよ〜」って言う状態ではありたかったし、そうするのに遠慮や後ろめたさがあっても嫌だし。
昨年末から今年の上半期は「月刊PHPカンファレンス」の到来に依るCfPマラソン地味たところもあり、この際には「多重応募をしがちな自分だから、出せるものを片っ端から出しました!!ってなると荒らしみたいになりそうだから、同一ネタでの重複応募は避けよう〜」というセルフ縛りを設けて臨んだり*2。
で、そのどちらの時期も抜けて今回、また「話たいことを書いて出すぞ〜」をしているのだけど。
そうしてみると気付くのは「何かをきっかけに脳みそがグルグル動いたり、盛り上がった話題がトークネタに昇華しやすいよね」っていう。改めて。
「おぉ、そういうことなんだ」とか「なるほど、つまりは・・・」みたいなリアクションとか思考が、自然と湧いてくるようなやつ。
自分なりの試行錯誤からでもいいし、本や他の人の発表を見たり聴いたりからでもいいけど、何かの「盛り上がり」をきっかけに「話したい・考えたい」に繋がるなぁ。
そういう意味では、「他人と話したり、誰かに教えたり」という機会から得るものは大きい。
そう思うと、「マネージャーになったから登壇できるネタが無くなった」は、あまり信じなくていいな〜ってやっぱり思う。めちゃくちゃ人と喋るし。
逆に言うと、プレイヤーだろうと他の役割だろうと、職場内で色々なコミュニケーションとか議論が生まれている環境では、ネタを発掘していくのにとても有利なんだろうな。
他方で、ごりごり「現場の第一線でコード書いてます」であっても、その働き方(コミュニケーションのあり方とか技術雑談的なものとか含む)や思考負荷によっては、インスタントにネタに「昇華」できるものを見つけにくそう。
っていうのを、77webさんの
fortee.jp
最近、チームに新しくjoinしたメンバーと議論したのをきっかけに、私が自分なりに定義し直した
を見かけて思ったりした。
向上心があって「今は分からないけど理解できるようになりたい」的な人が身近にいると無限プロポーザル製造マシンになれそう。
あともう1つ、「仕事でやっていることと外で話せることは違っても良い」っていうのも思う。
コードレビューと同じ。「自分の事は棚に上げて話す」みたいなのも大事じゃないか。
というか「社内勉強会みたいなのがあったとしても、こんなの話す価値はないだろうな」っていうのがありそうだなーとか
「社内の人に言うのは気が引けるけど、社外の人に話を聞いてもらいたい!!」っていうのもありそうだなーとか。
嘘をついて良いとか話を盛っても良い、とかって事ではない。語る内容についての誠実さは備えている必要がある。
誰向けの話なのか〜とか、どういう人が聴けると嬉しそうなのか〜〜とか。届けたい先が誰か?によって、話たいことが変わるはず。
実際、今の自分が「コード品質」とか「生産性、開発速度」とか「仕事術」「コミュニケーションの工夫」とかって話を同僚の前でしようものなら・・・っていうのは恐ろしくて考えたくもない。やるとしたら25分間沈黙土下座のほうがふさわしそう。
でも、「コミュニティに出ていく」っていうのは、自分じゃない誰かに届ける面白さがあって、その「誰か」の範囲も多様性もでっけぇですからね。発表する価値は生まれると思うし、もっと言えば「発表を聞く価値があったか」は受け手の中で生まれるものだし。
「身近な人にすら話す価値がないこと、話せないこと」でも胸を張ってやって良いじゃん!!!!!って思う。
ちょっと別の観点では、「うまく行ったこと」に限らなそうだな〜っていうのもあるか。
自分の中の思考実験とか思想的なもの、「こういう事を思った!如何か!?」って問う、みたいな。
カンファレンスが別に「お手本集」である必要もないはずだしな。参考事例というより「検討考察や議論に値するケースの集合」であっても、面白いはず。
(もちろん、ここでも内容についての誠実さを欠いてはいけないけど。)
この辺りの感覚は、自分の場合、「よい考え方や視点を与える」って意識よりも「何かを考えてみるとか、知ってみようと思うきっかけになってくれれば良いよね〜」的な気持ちで登壇することが多いからかも知れない。
なんでこんな事を考えたか。。。
ちょっと前まで自分が「栄養源」にしていた、他人との会話で挙がった話題とか誰かに教えたテーマ〜〜みたいなものや、実務を通じて「自分が成功していること」みたいなのが無いぞう〜〜どうしようかなーってなり。
なので、あんまり実生活とは関係のない趣味的な所からの発想ばかり目についたのだけども。
でも「議論をふっかけようとまでは思わないけど、自分なりに思索にふけっていることや理想を抱いている部分はあるな」「それを出しちゃえばいいか??」って、昨日くらいに思い始めたから、って気がする。
少し視点を変えてプロポーザルネタを発掘してみようかな、的な。